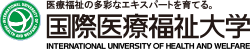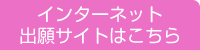- Q1理学療法士を目指しています。4学部に理学療法学科がありますが、違いはありますか?
-
A
理学療法士として必要な知識や技術を4年間で学ぶ、という内容に違いはほとんどありませんが、4学部は地域やキャンパスの学科構成が異なります。
「たくさんの学科と伝統がある大田原キャンパスがよい」、「海外経験豊富な教員がいる成田キャンパスがよい」、「交通の便がよい小田原キャンパスに通いたい」、「関連病院が近い大川キャンパスで学びたい」など、学部選択の理由はさまざまです。
特待奨学生特別選抜、一般選抜前期、大学入学共通テスト利用選抜[前期/後期]は、学部間の併願も可能です。その他の学科も同様です。 - Q2文系のクラスに所属していて、理数系科目を履修していません。受験や入学後の授業が心配なのですが...。
-
A
文系・理系を問わず、医療福祉の分野を志す方に幅広く入学してほしいと考えています。
学科により異なりますが、多くの学科の試験科目は、文系・理系を問わず受験できるように設定されています。
また、入学後の授業では総合教育科目を開講しており、専門科目を学ぶうえで必要になる理数系科目の知識を基礎から学ぶことができます。
- ※放射線・情報科学科および薬学科の試験科目には、理数系科目を含みます。
- Q3身体に障害がある場合、受験や入学の際に制限はありますか?
-
A
受験および入学後の修学・学生生活において、個々の障害に応じて特別な配慮が必要となる場合があります。詳細は「身体等の障害に伴う受験上および修学上の配慮について」を確認してください。
- Q4入学願書を取り寄せたいのですが...。
-
A
学生募集要項は本学ホームページからダウンロードしてください。または、オープンキャンパスや本学主催の進学相談会、見学会等の参加特典として配布していますので、ぜひ、本学イベントに参加してください。
- Q5過去問題集はどのようにすれば入手できますか?
-
A
詳しくは、【入試ガイド2026】P.15
 を確認してください。
を確認してください。
- Q6受験したい入試区分の科目試験が過去問題集に掲載されていません。どのように対策をすればいいでしょうか?
-
A
「大学入学シリーズ」(以下赤本)には本学の特待奨学生特別選抜と一般選抜の過去問題が掲載されていますが、これらと同様の出題傾向や出題形式になっている入試も赤本で対策できます。 赤本で対策できる入試については、【入試ガイド2026】P.14
 を確認してください。
を確認してください。
- Q7特待奨学生特別選抜の過去問題は一般選抜前期の対策にも利用できますか?
-
A
利用できます。
いずれも同様の出題傾向や出題形式になっています。 - Q8地方試験場で受験したいのですが、試験場によって合否に不利になることはありますか?
-
A
一切ありません。
最も受験しやすい試験場を利用してください。 - Q9選択科目を受験する場合、選択する科目によって合否に不利になることはありますか?
-
A
一切ありません。
科目ごとに点数を偏差値化して合否を判定します。 - Q10遠方から受験しようと考えているのですが、宿泊先は紹介してもらえるのでしょうか?
-
A
本学から紹介はしていません。
- Q11感染症に罹患し、試験当日に欠席した場合、入学検定料の返金や振替受験等の措置はありますか?
-
A
まずは各キャンパス入試事務室に連絡してください。可能な限り、他の入試区分への入学検定料の振替を行います(返金は行いません)。
- Q12試験当日、昼食を持参した方がいいでしょうか?
-
A
持参することをお勧めします。
昼食は、昼休みに試験室内で食べることができます。試験場によっては近くにコンビニエンスストアもありますが、休憩時間が限られていますので、持参した方がよいでしょう。 - Q13募集人員が「若干名」の入試区分については、例年どれくらいの合格者数ですか?
-
A
昨年度の合格者数は【入試ガイド2026】のP.46~47に記載していますので参考にしてください。出願状況などを考慮して合格者を選抜していますので毎年何人という決まりはありません。
- Q14合格発表はどのように行いますか?
-
A
合格者には、「合格通知書」を送付します。学内掲示による発表は行いません。
また、インターネット出願サイトの「マイページ」でも合否結果を確認することができます。 - Q15「学生募集要項」の合格発表 <合格発表上の注意>の項目に、「志望した学部・学科以外で合格する場合があります(志望した学部・学科で不合格となった場合に限る)。」とありますが、どのような場合に志望以外の学部・学科での合格が出るのでしょうか?
-
A
本学では、「学生募集要項」の記載に基づき、入試当日に「他学部・他学科に関する志望調査」というかたちでアンケートをとり、出願時に志望した学部・学科以外にも進学を検討しても良いと考える学科があるかどうかをあらかじめ確認しております(応募状況によっては調査を行わない場合もあります)。
受験いただいた学部・学科が不合格となった場合で、なおかつ試験成績が上記の志望調査で進学を検討しても良いと考える学部・学科※の合格基準に達している場合については、合格発表後に改めて該当学科に進学する意思があるかどうかを受験生および保護者様に確認をとった上で合格とすることがあります。
※各学科の志願状況・手続状況によっては、志望調査で回答された学科以外の学部・学科についても進学の意思を確認させていただく場合があります。 - Q16入学手続をした後、入学を辞退することはできますか?
-
A
併願制入試に合格した場合(専願制入試合格者が特待奨学生特別選抜にチャレンジ受験をして合格した場合を除く)のみ入学を辞退することができます。
本学の入学手続をした後で入学を辞退するには、別途定める辞退期限までに入学辞退届を提出する必要があります。この場合、入学金以外の学生納付金が返還されます。 - Q17成績開示はできますか?
-
A
特待奨学生特別選抜、一般選抜前期、一般選抜後期では不合格者を対象に成績開示を行っています。
詳細は本学ホームページ内受験生応援Naviを確認してください。
入試Q&A
入試に関するQ&A (医学部を除く)
入試全般
総合型選抜[Ⅰ期/Ⅱ期]
- Q1受験するためには高校の推薦が必要ですか?
-
A
「自己推薦」形式の入試のため、高校の推薦は不要です。ただし、合格したら必ず本学へ入学することが出願の条件になります。
- Q2受賞歴や特別な資格を持っていないのですが、総合型選抜[Ⅰ期/Ⅱ期]に出願できますか?
-
A
受賞歴や資格がなくても出願できます。ただし、出願書類の「活動実績報告書」は全員提出の書類となりますので、記載する資格や活動がない場合でも「記載事項なし」を選択して提出してください。
尚、本学のオープンキャンパスや説明会に参加した実績を記載しても構いません。 - Q3病院見学会に参加しないと総合型選抜[Ⅰ期/Ⅱ期]を受講できませんか?
-
A
保健医療学部看護学科、小田原保健医療学部看護学科、福岡保健医療学部看護学科を受験する方は病院見学会への参加が必須です。上記以外の学部・学科を受験する方は、参加は不要です。
- Q4看護学科が第一志望学科ではないのですが、総合型選抜[Ⅰ期/Ⅱ期]出願希望者対象の病院見学会に参加できますか?
-
A
総合型選抜に出願する予定がない方および第一志望学科が看護学科以外の方は病院見学会に参加できません。ただし、看護学科と他学科の間で第一志望学科として出願する意思が少なからずある場合は、病院見学会に参加してください。
- Q5総合型選抜[Ⅰ期/Ⅱ期]で出題される「適性をみるための基礎試験」とはどんな試験ですか?
-
A
英語・国語・数学・理科の基礎的な知識を問う問題や、グラフや統計資料などから読み取った内容をもとに自分の考えを述べる小論文が含まれます。試験時間は90分を予定しています。
- ※総合型選抜[Ⅰ期/Ⅱ期]で出題する「適性をみるための基礎試験」は、オープンキャンパスや本学が主催する進学相談会・見学会等で希望者に対し配付しています。
- Q6薬学部・福岡薬学部の「適性をみるための基礎学力試験」とはどんな試験ですか?
-
A
「英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、論理・表現Ⅰ」、「化学基礎」、「生物基礎」の基礎的な問題になりますので、高校の教科書を復習したり、本学の赤本に掲載されている一般選抜の英語・化学基礎・生物基礎の問題を解いてみるのもよいでしょう。試験時間は120分、解答形式は記述式+選択式を予定しています。
- ※過去問題は非公表です。
- ※成田薬学部では総合型選抜[Ⅰ期/Ⅱ期]は実施しません。
- Q7総合型選抜[Ⅰ期]や学校推薦型選抜で不合格になった場合、総合型選抜[Ⅱ期]に出願できますか?
-
A
できます。
学校推薦型選抜
- Q1学習成績の状況が3.4ですが、学校推薦型選抜[公募制]に出願できますか?
-
A
本学の学校推薦型選抜[公募制]は出願資格に記載の通り、医療福祉学部と赤坂心理・医療福祉マネジメント学部(医療福祉マネジメント学科のみ)、福岡保健医療学部 全学科については高等学校での全体の学習成績の状況(評定平均値)が3.0以上の方を対象としていますので出願できます。その他の学部では3.5以上の方を対象としていますので、この基準を下回っている場合には出願できません。
- Q2学校推薦型選抜[公募制]に出願できるのは、現役生だけですか?
-
A
高校卒業後1年未満の方も出願できます。もちろん、既卒生が現役生に比べ不利になることは一切ありません。
- Q3学校推薦型選抜[指定校制]に出願したいのですが、指定されている高等学校を教えてください。
-
A
[指定校制]については本学が指定する高等学校に直接通知します。指定の有無や試験内容については、高等学校の進路指導室に確認してください。
- Q4総合型選抜[Ⅰ期]を受験しましたが、不合格でした。学校推薦型選抜に出願できますか?
-
A
学校推薦型選抜[公募制]への出願は可能です。
ただし、総合型選抜[Ⅰ期]で不合格となった方は、学校推薦型選抜[指定校制]で全学部全学科に出願できません。学校推薦型選抜[指定校制]に出願を検討している方は、十分に注意してください。 - Q5学校推薦型選抜は[公募制]であれば、入学辞退は可能ですか?
-
A
入学辞退はできません。[公募制][指定校制]とも専願制入試のため、合格したら必ず本学へ入学していただきます。
- Q6高校での学習成績の状況(評定平均値)は、どの程度合否に影響するのですか?
-
A
学習成績の状況(評定平均値)はあくまで出願の際の基準として設定しているものです。
合否の判定にあたっては、試験当日の成績を重視していますが、出願書類の記載事項なども参考にし、総合的に判定します。 - Q7学科適性試験[基礎学力試験]とはどんな試験ですか?
-
A
一問一答式の問題が中心です。出題レベルは高校1年生くらいまでの教科書基礎・標準問題が中心です。オープンキャンパスなど本学が主催するイベントで過去の「出題例」を配布していますので、参考にしてください。
特待奨学生特別選抜
- Q1既に実施された入試を受験していなくても特待奨学生特別選抜を受験できますか?
-
A
受験できます。
初めて本学の入試を受験する方も特待奨学生特別選抜に出願できます。一般選抜と同様の出題形式と出題傾向になっていますので、併願制入試で受験する場合は特待奨学生特別選抜から受験することをおすすめします。 - Q2総合型選抜[Ⅰ期]、学校推薦型選抜[公募制/指定校制]などの専願制入試で既に合格し、入学手続をしている場合でも、特待奨学生特別選抜を受験できますか?
-
A
受験できます。
特待奨学生特別選抜の出願までに専願制入試などで合格し入学手続をした方は、同一学部・学科に限り、入学の権利を確保したまま特待奨学生特別選抜にチャレンジ受験ができます(この場合の入学検定料は10,000円になります)。
特待奨学生特別選抜で成績上位合格者になった場合、特待奨学生に選抜されます。 - Q3チャレンジ受験の結果、特待奨学生にならなかった場合、入学に影響することはありますか?
また、その後入学を辞退することはできますか? -
A
入学に影響することは一切ありません。また、専願制入試合格者は入学を辞退することはできません。
- Q4薬学部を志望しているのですが、特待奨学生Sは成績上位合格者の最大20人を、特待奨学生Aは特待奨学生Sに続く成績上位合格者の最大30人を対象とするということは、成績が1位~20位まで、21位~50位までということですか?
-
A
特待奨学生は、「合格者のうち、成績上位者であり、試験結果の科目合計得点率が60%以上(特待奨学生Sは80%以上、Aは70%以上)であって、本学がふさわしいと認めた方を対象」としています。特待奨学生特別選抜で薬学部を受験した場合、特待奨学生Sであれば300点満点中240点以上、特待奨学生Aであれば300点満点中210点以上の得点を収めていなければ、特待奨学生Sや特待奨学生A、特待奨学生Bとなる順位内であっても、対象とはなりません。
- Q5 特待奨学生特別選抜に出願できるのは1学部のみですか?
-
A
特待奨学生特別選抜では、最大7学部を併願することが可能です。出願したすべての学部で合否判定を行いますので、複数学部で合格する可能性もあります。
- Q6 特待奨学生Sと特待奨学生Aの人数に上限がありますが、上限に満たない場合は選抜される特待奨学生の人数が減りますか?
-
A
特待奨学生Sと特待奨学生Aの人数が総数に満たない場合、科目合計得点率60%以上の方から特待奨学生Bを選抜します。
一般選抜/
大学入学共通テスト利用選抜[前期/後期]
- Q1特待奨学生特別選抜で一般合格者になった場合、再び特待奨学生を目指して受験することはできますか?
-
A
受験できます。
特待奨学生特別選抜で入学手続をした方は、入学の権利を確保したまま、特待奨学生を目指して一般選抜前期、大学入学共通テスト利用選抜[前期]を受験することができます(この場合は正規の入学検定料が必要です)。
一般選抜前期、大学入学共通テスト利用選抜[前期]で成績上位合格者になった場合、特待奨学生に選抜されます。 - Q2総合型選抜[Ⅰ期]、学校推薦型選抜[公募制/指定校制]の合格者が一般選抜前期や大学入学共通テスト利用選抜[前期]にチャレンジ受験はできますか?
-
A
受験できません。
- Q3一般選抜前期と大学入学共通テスト利用選抜[前期]は1組の出願書類で出願できますか?
-
A
出願できます。
一度の出願登録で、両入試区分に出願する場合、出願書類は1組でかまいません。 - Q4保健福祉系学部と薬系学部は併願できますか?
-
A
一般選抜前期は3日程あります。1日の受験で併願することはできませんが、受験日を変えてそれぞれ受験することが可能です。もちろんそれぞれに大学入学共通テスト利用選抜[前期]を組み合わせて併願できます。 特待奨学生特別選抜や一般選抜後期では、保健福祉系学部と薬系学部を併願することができません。
- Q5入学検定料割引制度について教えてください。
-
A
大学入学共通テスト利用選抜[前期]では、同一学部の一般選抜前期複数日程と合わせて出願する場合、入学検定料は10,000円になります。同一学部であれば、第一志望の学科が異なっていても、割引制度が適用されます。
- Q6一般選抜前期の選択科目は120分で2科目受験となっていますが、解答順や時間配分はどうなりますか?
-
A
解答順、時間配分とも試験時間内で自由に設定できます。
- Q7一般選抜前期の各日程(日程A・B・C)に違いはありますか?
-
A
試験日ごとに出題される問題は異なりますが、傾向や出題形式は同様です。試験日を複数日設定し、受験者が自由に選択できるように受験の機会を広げています。日程により、実施する地方試験場が異なります。
- Q8一般選抜前期は複数回受験できますか?
-
A
複数回受験しても特定の日程を1回受験してもかまいません。
同一学部・学科を複数回受験した場合は、最も成績の良い試験日の結果を合否判定に使用します。 - Q9一般選抜前期や大学入学共通テスト利用選抜[前期]で補欠候補者となった場合、一般選抜後期や大学入学共通テスト利用選抜[後期]に出願できますか?
-
A
出願できます。補欠候補者の繰上の有無や繰上時期については、合格者の入学手続状況によって異なりますので、本学への入学の希望が強い方は、出願していただくことをおすすめします。
なお、併願制入試で合格し入学手続きを完了した方も、手続をした学部・学科とは別の学部・学科を第一志望として出願することが可能です。
併願制入試共通
- Q1同一学部の理学療法学科と作業療法学科の両方に合格できる方法はありますか?
-
A
どちらか一方の学科を第一志望としている場合、第二・第三志望制度を利用することで、もう一方の学科を第二志望学科として選択することが可能です。ただし、第一志望学科で合格基準に達した場合は、第二志望学科の合否判定は行いません。
両学科とも第一志望としている場合、一般選抜前期では日程ごとに第一志望学科を変更することが可能です。例えば日程Aで保健医療学部 理学療法学科、日程Bで保健医療学部 作業療法学科を第一志望学科として選択した場合、両方の学科で合格する可能性があります - Q2第二・第三志望学科を選択できる入試はどの入試ですか?
- A
- Q3特待奨学生特別選抜や一般選抜前期で薬学部、成田薬学部、福岡薬学部をそれぞれ第一志望とした場合と第二・第三志望制度を利用した場合、何か違いはありますか?
-
A
3学部を第一志望とした場合、各学部の合格基準に達していれば3学部に合格できます。一方、第二・第三志望制度は、第一志望学部で合格基準に達した場合、第二・第三志望学部の合否判定は行いません。
また、2学部を第一志望とした場合、入学検定料は70,000円です。第二・第三志望制度の場合は追加の入学検定料はかからないため35,000円です。 - Q4特待奨学生特別選抜や一般選抜前期の選択科目は、事前に決めて出願時に申請する必要がありますか?
-
A
すべての入試において選択科目の事前申告は必要ありません。特待奨学生特別選抜、一般選抜前期では、試験当日、問題を見てから解答する科目を選択できます。
- Q5放射線・情報科学科を第二・第三志望学科で登録した場合、試験科目は放射線・情報科学科の選択科目 を選択する必要がありますか?
-
A
その必要はありません。第一志望学科で指定されている 試験科目を受験してください。必ずしも放射線・情報科 学科の選択科目を選択する必要はありません。第二・第 三志望学科の合否判定は第一志望学科の試験科目で行います。
- Q6特待奨学生特別選抜と一般選抜前期で医療福祉学部と保健医療学部に出願する予定です。
選抜方法は、2科目型と3科目型のどちらで受験すればいいでしょうか? -
A
医療福祉学部など2科目型の学部・学科の志願者が、同一試験日に3科目型の学部・学科を併願する場合、3科目型で受験する必要があります。
- Q7特待奨学生特別選抜や一般選抜前期において、選択科目2科目を現代の国語・言語文化と日本史探究で受験できますか?
-
A
医療福祉学部および赤坂心理・医療福祉マネジメント学部のみを受験する場合であれば可能です。他の学部では2科目のうち1科目は必ず英語を解答する必要があります。
- Q8特待奨学生特別選抜や一般選抜前期において、選択科目は120分で2科目受験となっていますが、解答順や時間配分はどうなりますか?
-
A
解答順、時間配分とも試験時間内で自由に設定してください。
- Q9総合型選抜[Ⅰ期/Ⅱ期]や学校推薦型選抜を不合格となった方で、特待奨学生特別選抜や一般選抜などを再受験し、合格した方はいますか?
-
A
毎年、合格する方がいます。選抜方法も異なるので諦めずに受験してください。
- Q10合格発表で補欠候補者と通知されました。繰上合格はどのように実施されますか?
-
A
補欠合格者は、合格者の入学手続状況により欠員が生じた場合に限り、繰上合格となることがあります。繰上合格については、本学より本人に原則として電話連絡の上、入学の意思を確認します。その場で電話に出られなかった場合でも繰上合格の順番が飛ばされることはありませんが、速やかに折り返し連絡してください。
特待奨学生制度(特待奨学生特別選抜・一般選抜前期・
大学入学共通テスト利用選抜[前期] 共通)
- Q1特待奨学生に選抜された場合は、いつごろ通知されますか?
-
A
対象者には、合格発表時に通知します。
- Q2特待奨学生に選抜された場合、他大学との併願ができなくなりますか?
-
A
併願できます。
また、特待奨学生に選抜されても入学を辞退することができます(専願制入試合格者が特待奨学生特別選抜にチャレンジ受験をして合格した場合は除く)。 - Q3特待奨学生に選抜された合格者が入学手続をしなかった場合、他の合格者が特待奨学生に繰り上がりますか?
-
A
繰り上がりません。
特待奨学生対象者は、合格発表時に通知された合格者のみが対象となります。 - Q4入学後に特待奨学生の権利がなくなることはありますか?
-
A
以下の項目のいずれかに該当した場合には、原則として その後の奨学金給付はありません。
- ・留年した場合(休学による留年を除く)
- ・転学科した場合
- ・学則で定める懲戒処分を受けた場合
- ・前年度の成績が不良の場合(前年度の学科内成績順位において、特待奨学生Sは下位50%、特待奨学生A、 Bは下位40%に入った場合)
- ・その他、奨学金給付を継続することが適当でないと学長が判断した場合
過去問について(医学部を除く)
下記以外にも、医学部を除く全学部・全入試区分の過去問題をオープンキャンパスで閲覧できます。
(データ流出や無断配布による著作権侵害のおそれがあるため、過去問題の撮影・コピーは認めておりません)
学科適性試験[基礎学力試験]
傾向と対策

- 学科適性試験[基礎学力試験]の難易度は、普段の高校での授業や日常生活で得られる知識で解答できるレベルです。

- 本学の学科適性試験[基礎学力試験]〈出題例〉を入手し、出題形式を把握しましょう。

- 高校の教科書や参考書を使用して、基礎的な知識を見直すことも有効です。
◎学科適性試験[基礎学力試験]〈出題例〉を入手する
学校推薦型選抜[公募制]および帰国生徒特別選抜で出題している学科適性試験[基礎学力試験]の〈出題例〉は、オープンキャンパスや本学が主催する進学相談会・見学会などで、参加者特典として入手できます。
小論文試験
傾向と対策

- 本学の小論文試験は、医療・福祉分野の専門的な知識の有無を問うことが目的ではありません。

- 首尾一貫した分かりやすい文章を、限られた時間内に指定された文字数でまとめられるかどうかがポイントです。
誤字・脱字のないように注意しましょう。

- 小論文テーマは幅広い分野から出題されます。普段から新聞やニュースに関心を持ち、よく取り上げられている内容はメモを取り、自分が感じたことなどを簡単にまとめる練習をしておくとよいでしょう。
◎過去に出題されたテーマについて書く
小論文試験の過去の出題テーマは、【入試ガイド2026】P.16![]() を確認してください。
を確認してください。
過去に出題されたテーマについて制限時間内に書き、高校の先生などに添削してもらうのもよいでしょう。
その他の科目試験
赤本で対策をする
本学の特待奨学生特別選抜と一般選抜(一部日程、一部科目)の過去問題は、教学社より出版されている「大学入試シリーズ」(以下赤本)にて公表しています。また、以下の科目試験は、特待奨学生特別選抜、 一般選抜と同様の出題傾向や出題形式となっています。対策の一つとして利用してください。
赤本を解く際は、受験予定の入試や志望学部の過去問題に限らず、掲載されている他の入試・他学部の過去問題も解いてみましょう。また、数年分の過去問題を解くこともおすすめです。受験予定の科目を一通り解き、本学の出題傾向や出題形式を理解したうえで演習問題等に取り組んでください。
-
※総合型選抜[Ⅰ期/Ⅱ期]で出題する「適性をみるための基礎試験」は、オープンキャンパスや本学が主催する進学相談会・見学会等で希望者に対し配付しています。傾向と対策については【入試ガイド2026】P.14
 を確認してください。
を確認してください。
赤本で対策できる入試
○一般選抜前期 ○一般選抜後期 ○特待奨学生特別選抜 ○社会人特別選抜 薬学部・成田薬学部・福岡薬学部/学力検査[英語・化学]
○学校推薦型選抜[公募制]・帰国生徒特別選抜 薬学部・成田薬学部・福岡薬学部/学科適性試験[英語・化学]※
- ※薬学部・成田薬学部・福岡薬学部「学科適性試験[英語・化学]」の試験時間は2科目で90分です。一般選抜より1科目あたりの試験時間が短い分、問題数が少なめになっています。